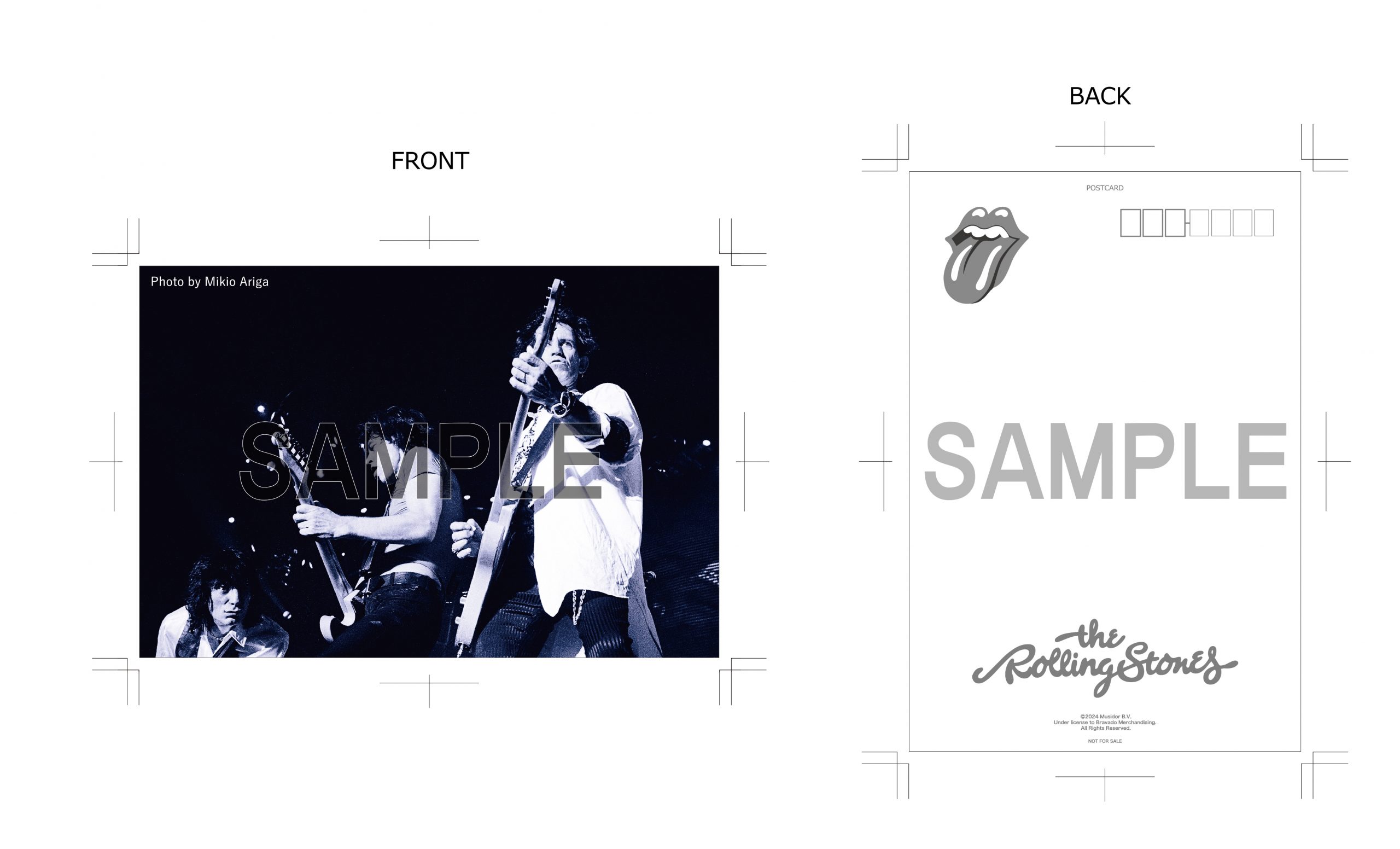年代別ストーンズLIVEの目撃者たち:総括編/寺田正典氏その3
『オン・エア』発売記念企画
年代別ストーンズLIVEの目撃者たち
ストーンズ初のBBC音源作品『オン・エア』の発売を記念して1962年にバンドを結成して以来、2017年の現在に至るまでライヴ活動を続けているストーンズのLIVEの魅力を実際に見ている方々の言葉で語っていただく本企画。
総括編その3。
元レコード・コレクターズ編集長であり、ストーンズ研究の第一人者である寺田正典氏が語る、世界最高のロック・バンド、ザ・ローリング・ストーンズのライヴ変遷のその3。
お楽しみください。
寺田正典(総括編)
世界最高のロック・バンド、ザ・ローリング・ストーンズのライヴ変遷(その3)
1980年代(1981~1982年)
~世界的ビッグ・アクトとしての成長と回顧の始まり~
81年の北米ツアーは少し間が空いたせいか、演奏パターンが70年代のそれとはまた微妙に異なるものとなりました。印象から言うと、サウンドがやや硬質になりました。メンバーの演奏自体の変化に加えて、恐らくPAシステムの側の変化もあり、高域がハッキリと押し出されたようなサウンドを聴かせるようになったことで変化が際立った面もあると思います。そんな中で、チャーリーが固く閉じたハイハットで以前よりステディに刻み(2拍、4拍の裏は除く!)、各曲中の演奏スピードの変動も減ったことで、ストーンズの演奏のテンポ感がかなり変わったという印象を受けた人も多かったのではないでしょうか。「ネイバーズ」や「レット・ミー・ゴー」といったハイ・テンポの新曲に印象が引っ張られた面もあるでしょう。ディレイなどのエフェクターの使い方もこなれてきて、キースのギターの音もアグレッシヴでありながらある種のニュー・ウェイヴ的な音の厚み、硬質さを感じさせるものに代わり、全体としてストーンズのサウンドはギラキラとした80年代的な質感を持ったものへと変化しました。それをより強調しつつ仕上げられたライヴ・アルバム『スティル・ライフ』のサウンドもあの時代に完全にマッチしたもので、日本でも新たなファン層を獲得するきっかけになったはずです。
セット・リストのなかに大幅に60年代の曲を入れてきたのも大きな意味を持っていたと思います。その中でも特に往年のファンの郷愁を誘っただろうと想像できたのが「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」で、映画『レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥギャザー』でも彼らの歴史と重ね合わせるような演出がなされていました。そのようにライヴの場で自分たち自身の“歴史絵巻”を見せるというようなことを始めたのがこのツアーからだと思います。「アンダー・マイ・サム」から始まり、「サティスファクション」で終わる66年のLP『ガット・ライヴ・イフ・ユー・ウォント・イット!』を思い起こさせる構成のライヴ・アルバム『スティル・ライフ』をリリースしたのも象徴的です(『ガット~』録音時のオープニングは「黒くぬれ!」でしたが録音に失敗したので収録されなかったという経緯があります)。そうしたノスタルジックな部分も含めた現在進行形のストーンズを提示しつつ、アウトロとしてジミ・ヘンドリックスの演奏によるアメリカ国歌「星条旗」を流したのは、自分たちが数少なくなってきたロック史の生き証人でもあり、ロックの歴史全体を象徴し、また背負って行くべき存在であることのアピールのようにも感じられました。もちろん、そうしたロックの歴史を体験してきた同年代の観客たちへの共感の表明でもあったのかもしれません。
ミック・ジャガーがアメリカン・フットボールのユニフォームを着用してステージに登場し話題になったように(全員の)衣装の色彩が一気に明るくなり、日本人アーティスト、カズヒデ・ヤマザキによるファンタジックなイラストが描かれた巨大な紗幕、飛び交うカラフルな風船などの存在も併せて、随分と明るいイメージで登場したものだと、最初に伝わってきた写真や断片的な映像を見て驚かされた記憶があります。メンバーもゴンドラに乗ってクレーンでステージから観客の上空まで昇っていったりとか、屋内会場では使われた回転ステージを使用するなど、ステージ・セットも一段と大掛かりで派手になってきました。当時のミックは38歳でしたが、自分の“老い”とどう戦うかということを意識し始めており、フィジカル・トレーニングを始めていていました。同じころアメリカで起こっていた、女優のジェーン・フォンダが主導したワークアウト・ブームとの関連も興味深いところなのですが、オリビア・ニュートン・ジョンの「フィジカル」とストーンズの「スタート・ミー・アップ」のプロモーション・ヴィデオの中のミックの姿が重なる部分があるのは、そういう背景もあります。
スポーティーなイメージをそのまま押し出すようになったことは、ツアーの演奏会場が完全にスタジアム・ライヴが中心となる中で、同じ会場でいつも行なわれているスポーツ・イヴェントとに通う好き層の共感も得ることでオーディエンスの拡大を図りたいとの意図があったのではないか? と勘繰りたくなります。実際、ストーンズは古くは70年ツアー中のミラノ公演でチャーリーが地元サッカー・チームACミランのユニフォームを着て現われたりしていた記録もあります。コンサートを盛り上げる手法のひとつとして地元スポーツ・チームのファンにそういった形でアピールするというのは、欧米では結構使われる手のようでもあります。そういうのが一番得意だったのは82年の西武球場でのコンサートで西武ライオンズのキャップを被ったフレディ・マーキュリーが「伝説のチャンピオン」を歌ったクイーンであったろう、と個人的には思っていますが。
衣装はともかく、ミックのアクションも(コンサートや映画を観た)多くの人に真似されたような独特のカクカクした特徴的なものとなり、観客席に飛び込むなどの大胆なパフォーマンスもありました。また、国旗を身にまとうなどの派手な演出にも驚かされました。ツアーの初めのころはアンコール曲として「ストリート・ファイティング・マン」と「サティスファクション」が交互に演奏されていましたが、次第に「サティスファクション」一本に固まっていったのも興味深く、アンコール(の最後)に「サティスファクション」を演奏してコンサートを終える、という黄金のパターンがそれ以降定着することになります。
82年のヨーロッパ・ツアーは81年ツアーを踏襲しながら『ライヴ・イン・リーズ 1982』の「アンダー・マイ・サム」でも確認できるように演奏がさらにテンポ・アップ。バンド全体の調子が良くなるとテンポ・アップしていく、というのはストーンズのコンサート・ツアーではよくあるパターンではありますが、それが極端に出たのがこの82年ツアーでした。ミックの衣装はますます派手な色合いのものになりますが、他のメンバーはそれぞれバラバラの恰好でしたね。この年から元オールマン・ブラザーズ・バンド~シー・レヴェルのチャック・リーヴェルがキーボードで全面参加。ツアー・リハーサル中にイアン・スチュワートからブギウギ・ピアノの手ほどきを受けた成果は、同じ『ライヴ・イン・リーズ1982』の「レット・ミー・ゴー」の演奏シーンで見られます。二人がひとつのピアノの前に座り連弾でプレイする美しいシーンです。イアンがストーンズのツアーに参加するのはこの年が最後(84年に死去)でした。
参考資料:『スティル・ライフ』『レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥギャザー』『ハンプトン・コロシアム〜ライヴ・イン 1981』『ライヴ・イン・リーズ 1982』
スティール・ホイールズ/アーバン・ジャングル・ツアー(1989~1990年)
~メンバー間の確執を乗り越えた復活ツアーとスキルの再構築~
89年の北米ツアーはミック・ジャガーとキース・リチャーズが確執を乗り越えた実現したストーンズの復活ツアーと位置づけられるものでした。まず思い起こすのは、あの『ブレード・ランナー』的とも言われた巨大な建築物にしか見えなかったステージ・セットですが、演奏面でも、ミックがソロ・ツアー(88年)で行なった様々な実験の成果が反映されていました。ストーンズとしてライヴ演奏を続けていくうえで、90年代に向け自分たちのスキルを再構築する必要に迫られた結果、ミックがソロ・ツアーで試した演奏スタイルのいくつかはストーンズにも導入することになったようです(バック・コーラス陣の参加、「悪魔を憐れむ歌」でのシーケンサーの使用など)がありました。そのため、同じ80年代でも、81、82年頃のライヴとはまったく違うものになりました。また、現在も採用しているチャック・リーヴェルとマットのキーボード2台体制もここがスタートでした。そのうちマット・クリフォードは、アンダーソン・ブラッフォード・ウェイクマン・ハウのサポート・メンバーだった若手マルチ・ミュージシャンで、彼が「ミス・ユー」ではサンプリング・キーボードによるハーモニカ演奏を聴かせたり、「無情の世界」ではCDからサンプリングしたコーラスを実際のコーラス隊の声に重ねて“弾い”たり、さらにはまるでイエスのコンサートか? と思われるようなインタールードをキーボードで奏でたりと、それまでのストーンズのコンサートでは考えられない大胆な試みを担当していました。またコーラス隊の加入で、「ダイスをころがせ」や「ギミー・シェルター」などで、スタジオ録音の時のものをほぼ踏襲したアレンジでステージ演奏することが可能になり、音のカラフルさ、わかりやすさといった要素に加えて、例えば60年代からのファンの琴線により触れるようなステージでの楽曲再現が可能となりました。
ただし、デジタル・キーボードまで使ったことでバンド・サウンド全体の音色バランスが変ってしまったことが賛否両論を呼んだのも確かでした。それでもリズム面では深化が見られ、バス・ドラムをスクエアな4つ打ちで鳴らしておきながら全体ではハネるというこの時代らしい(ハウス・ミュージック的でもある)ビート感が、ツアー・スケジュールをこなしながら段々と完成されていきました。そのビートがもっとも効果的に使われていたのが、コンサート本編最後で演奏されていた「サティスファクション」で、そんな新しいビートにオーティス・レディング・ヴァージョンのアレンジを施されたホーン・セクションが乗ることでソウルっぽさも加わった絶妙な演奏を聴かせてくれました。最近の演奏ぶりと比べると随分とテンポが速い演奏が多いものの、無理をしている感じはありませんでした。キースの独特の決めアクションもキレがあり、それを毎回効果的に巨大スクリーンにタイミングよく映し出すカメラマンたちとの息もピックリで、大会場のオーディエンスを飽きさせないメリハリの効いた演出としても成立するようになっていました。ステージのミックが通常立っている位置には、足を滑らすことも可能な板がはめ込んであり、それを使ったシャープなステージングもお見事。しかし残念ながら、70年代のように、1本のマイクを挟んでミックとキースの両雄が並び立つ姿はほとんどなくなってしまいました。と同時に、81~82年ツアーの頃から薄れ始めていた、かつてのような妖艶さも見られなくなりました。肩パットなんかも入った衣装も日本の時代感覚で言うところのバブリーなスタイルに見えました。コンサートの最後に毎回整列して挨拶するようになったのもこのツアーからですね。
続く90年のツアーは、日本のファンにとっては忘れられない2月の東京ドーム連続10回公演から始まりました。89年後半の演奏の好調ぶりはそのまま受け継がれますが、89年は大都市公演のみの参加だったアップ・タウン・ホーンズ(彼らが不在の公演でもサンプリング・キーボードによるホーン・パートの演奏はありました)が全公演帯同でパワー・アップしました。5~8月のヨーロッパ・ツアーからは、コーラス隊もメンバー・チェンジ。〈アーバン・ジャングル〉という新たなツアー・タイトルを冠し、ステージ・セットもシンプルなものに変更されました(日没が遅い地域の野外ステージが多かったこと、国による電源事情の違いなどに備えてのことと言われています)。演奏そのものは90年に入ってさらによくなった印象があり、ヨーロッパの衛星放送で放映された(日本でも後にBSで放映)バルセロナ公演はこのツアーのハイライトとも言える素晴らしい演奏を披露していました。ところがこの年開催されたサッカーのワールド・カップの日程とのバッティングが原因で、イタリアで一部不入りの公演が出たり、イングランド代表チームの試合とロンドン公演の時間が重なって、コンサート中に得点が入ってオーディエンスがざわついてしまう、といったトラブルもありました。ミック自身がサッカーやクリケット好きということもありますが、おそらくこの経験を経てストーンズは日程的にも、行き先々のスポーツ・チームのファン層からの共感を得るという意味でもスポーツ・イヴェントとのより効果的な連携について一層、考えるようになったのだと思われます。それは後の2006年、ミラノで行なわれた『ビガー・バン』に伴うツアーのヨーロッパ公演初日のステージにおいて、その2日前に終了したワールド・カップで優勝したイタリア代表チームの選手をステージに上げて祝福したりすることにつながっていきます。
参考資料:『フラッシュポイント』『アット・ザ・マックス〜スティール・ホイールズ・ツアー90』
インタヴュー&テキスト: 山田順一