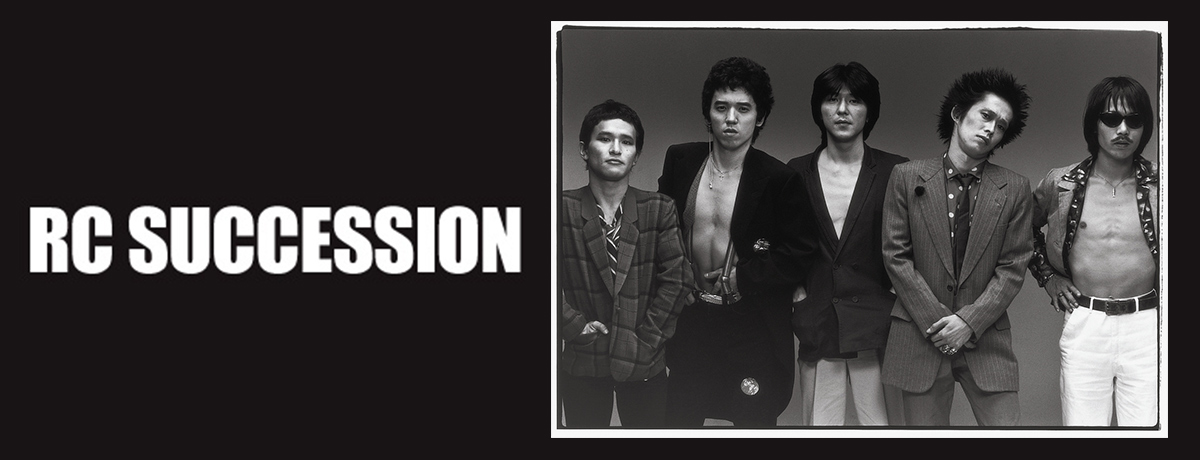1983年、RCサクセションは大きなバンドになっていた。前年の忌野清志郎&坂本龍一「い・け・な・いルージュマジック」のヒットで清志郎は名実ともにスーパースターになり、一般社会で誰でも知っている超有名人となった。そして、RCサクセションは初のシングルヒット「Summer Tour」を放ち、アルバム「BEAT POPS」はヒットチャートの2位に輝いた。異端が切り開いたケモノ道は王道になり、いつしか高速道路にクロッシングしてしまった。居心地が悪そうにテレビや雑誌に出ている表情に、チャーミングな共鳴を感じとった全国のティーンエイジャーたちが、かつて体験したことのないうねりとなって、RCサクセションを追いかけた!コンサート会場、スタジオ、出演しているテレビ局やラジオ局、ツアー先で宿泊しているホテルや移動中の新幹線や飛行機の中まで!プライベートで変装して外出しても、ひとたび見つかれば、アッという間に街はパニックになった。もう電車にも乗れない、バスなんてとんでもない!車でもドライブ・インにすら入れない。コンサート会場には清志郎やチャボのようなファッションの少年少女たちが集まり、とりわけ少女たちが圧倒的に増えて、その後、清志郎のライブに女性が多くなったのも、この時期がきっかけとなった。屋根裏から出てきた道化者たちは、報われない10代のヒーローズとなったのだ。
そんな状況とは裏腹に、バンドの内情は大変な局面を迎えていた。想像を絶するハードスケジュールとリリース計画に清志郎は体調を崩し、レコーディングも難航を極めた。やっとの思いで完成させたアルバム「OK」は、全体的に明るい曲調ではあるが、作品の根底には夜の海のような哀愁が漂っていた。シングルカットされた「Oh! Baby」が、当時、人気のあったラジオ番組でオンエアーされた際、番組の看板である女子大生DJが号泣したことが報道された。80年代では奇異な出来事であった。原因はわからないが、ひょっとしたら彼女はこの歌の行間から滲み出てきた、ある種の感情にアジャストしてしまったのかもしれない。あらゆることがニュースになり、バンドマンからアーティストと呼ばれ、時の人たちもこぞってRCサクセション支持者となり、RCを好きだと言うことがカッティングエッジでかっこいいと思わるようになった。時代は来るべき狂乱のプロローグに入る。ワープロや電子手帳が発売され、ファミコンが登場!テクノカットでピアスをあけた抜け殻のようなゾンビたちが、時代にさえ乗っていれば安心とばかりに没個性化へ。現代の人工知能を予期するように、人は思考を停止して、時代の機嫌に左右されるようになった。好きなものを好きだと言えないファシズムに覆われ、まるで2016年のように退化した。何物にもつかまらない、型にはまらない!RCサクセションは時代の気まぐれからスペースアウトした!そろそろ流れを変える時に来ていた。
本作品はその真っ只中の貴重なライブ映像だ。日本ではじめて成功したロックンロールバンドの頂点の記録である。点から線になり面になったバンドが作った日本のR&Rエンターテインメントの基本形であり、雛形。後のインタビューで、この時期のことを清志郎はひどく苦しい季節として、精神的にも肉体的にも記憶している。ライブは物語であり、人の生き方になることが一目瞭然でわかる作品である。
そして、何より重要なのは、ここからチャボがサウンド的に変化して、清志郎のヴォ―カルとぶつかりあうギターになったことだろう。それまでのRCサクセションは常に歌バンとしてのアンサンブルを基盤としてきたが、この時期からチャボのギターが飛び出してきて、清志郎のヴォーカルと絡んだりぶつかりあったりして、その後のRCの専売特許となる「日本語の跳ねるロック」を誕生させたのだ。ビートルズやストーンズを手本とした歌バン・アンサンブルからはみ出したサウンド。これはとても大きな功績である。世界中探しても見当たらない。ロックンロールの偉大なる発明で、その後の日本のロックンロール・バンドマンたちへの意識的、潜在的にかかわらず最強の遺伝子レベルでの影響を及ぼしていることは間違いない。
なぜこのようなサウンドになったのか?元々、RCサクセションは、ロックンロール、ブリティッシュビート、リズム・アンド・ブルース、サザン&ノーザンソウル、フォークビート、アメリカンポップス、アーシ―、レイドバック、レゲエ、ダブ、セカンドライン、アートロック、サイケデリック、パンク、ニューウェーブ、ノーウェーブ、フリージャズ等、あらゆる音楽をぶちこんだミクスチャーのオリジネイタ―であり、オルタナティブのフロンティアである。禁じ手なし。ストーンズのフォーマット=ミックとキースの役だけは決めて、そこから発信する自由な挑戦で数々の型にとらわれない名曲を生んできたのだ。ジャンルやカテゴリーが好きで、ビジョンやブランドで安心する洋楽至上主義の日本人ロックリスナーは戸惑った。ストーンズでもないし、ロックンロールでもないし、ブルースでもソウルでもなく、ポップスでもない。一体、この音楽は何なんだ???
主に清志郎のソングライティングの意外性も大きいが、途中からチャボもG2も、メンバーが曲作りに参加しているところを考えると、元祖オルタナティブサウンドは確信犯であったのかもしれないとさえ思わせる。その証拠に「BEAT POPS」で決定的となったG2のエレクトロ音楽と鍵盤的見地からのアレンジメント=RCサクセションのアナザー・サイドは、見事なまでに時代へのアバンチュールに成功している。狙いは的中し、ビッグセールスに結びついた。日本のロックバンドとして前人未到の地に到達したのだが、前例を好まない清志郎とチャボは完璧という概念を拒否することからはじまる景色があることを知っていた。ここからどこに行くか?その風穴を開けたのがチャボだった!RCサクセションの黄金律に戻り、ストーンズのフォーマットからストーンズにはないものを選び出し、清志郎の言葉のリズムと相反するオフビートを主体とした跳ねるギター=日本語の跳ねるロックを発明したのだ。母国語が跳ねるロック。これは英語圏のバンドには極めて少ない。なぜなら、日本語の言葉のリズムから編み出した弾き方であり、特に清志郎のように言葉数の少ない、行間にいくつもの感情が入るソングライターの場合には、とても有効なサウンド・グラデーションを発色させる。チャボは、アメリカのまだ言葉が少なかった頃の戦前のカントリーブルースやジプシー音楽あたり、たとえばチェット・アトキンスやジャンゴ・ラインハルトからヒントを得たのかもしれない。豊かな表現力を手に入れたロマンティックなソウルミュージックではなく、もっと源流を目指したのだ。作家 村上春樹氏も「職業として作家」の中で取り上げている、元祖アウトサイダー ロバート・ハリス氏の著書「アフォリズム」にある、ポ―ランドの詩人 ズビグニュエフ・ヘルベルトの名言につながる。「源泉にたどりつくには流れに逆らって泳がなければならない。流れにのって下っていくのはゴミだけだ」。
仲井戸“CHABO”麗市の発明した「言葉が跳ねるロック」。本作品はその魅力が実にわかりやすく、全面に出ている。当時の収録状況やマスターの問題から、カメラ数も3台と少なく、画像も荒い箇所が散見される。だからこそ、いままで見ることのできなかった音が鮮やかに映し出されているのだ。清志郎の声と言葉が、チャボのギターの音に絡まったり、ぶつかりあっているのが、はっきり手ごたえとして感じる!これは本当に凄いことだ!よかったら、そこだけに神経を集中して見て聴いてほしい!ロックンロールサウンドのアウトサイド=新しい景色を描いたチャボの功績を、いまこそ堪能して、評価してほしい!こんないかしたギタリストとおんなじ時代、おんなじ国に生まれてしあわせだぜ!
テキスト:高橋ROCK ME BABY